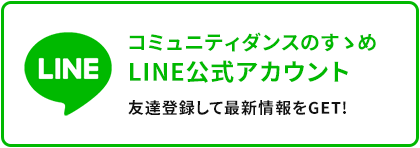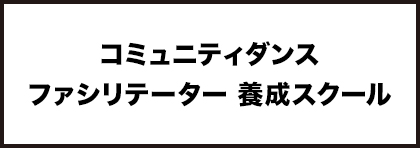砂連尾理・北村成美インタビュー 1部【コミュニティダンスのすすめ】パンフレットより
第一部
- お二人は、地域の方たちとのダンスの活動(コミュニティダンス)が現在のように広がってくるかなり前から、地域の人との活動をされていて、今も様々な形で継続されています。それぞれの活動について、お話を伺います。
―まず北村さんから。今日、北村さんの滋賀で行われているWSを見せていただきました。舞台作品やご自身のソロ作品を創る以外に、今日のような地域の人、障がいのある方などとの活動を始めるきっかけは、何だったんでしょう?
北村:まず、観客を巻き込むタイプのパフォーマンスを作品の中でやり始めたので、自分のソロ活動とすごく併走しているところがあります。 一つの事業としては、今日佐東さんが見て下さったWSが8年目なのですが、この知的障がいを持つ方たちのWSに講師として参加したのが初めてです。きっかけは、ダンサーの岩下徹さんのご紹介です。岩下さんは滋賀県の湖南病院というところでダンス療法をされていて、そのつながりで、滋賀県社会福祉事業団が発表会つきのWSを通年でやって欲しいという依頼をされたんですけど、岩下さんは、「僕は振り付けをしないので、そういうことにふさわしい人を紹介します」と言って、何故か私を紹介してくださった。その時、私は岩下さんと殆どお話しをしたことがなく、顔見知り程度だったので、未だになぜ岩下さんが私を指名されたのか分からないんですけど。でもそうやって言って下さった以上、それは有無を言わさずやろうと決めて。
WSを頼まれたとき、ダンス教室とかバレエ教室でダンスを教える経験はあったんですけど、ダンスWSとダンス教室の違いすら全然わからなかったので、実は相当どうしようかと悩みました。ただ、私自身は作品を創ってその場にいる人たちと一緒に楽しむ、みたいなことを始めていたので、そういうことだったら出来るかなと、自分がその時わかることのみで始めました。最初の頃のWSで、癲癇の発作を起こした方がいて、それを見てパニックを起こす人がいて、さらにそれを見て職員さんがウワーッて慌ただしく動く、けど事業団の担当の方には、「北村さん、続けてください。」って言われて、もう、どうなるんや~という感じで始まったというのが、実際のところです。
その当時の初回のWS映像を、たまたま最近になって見たんですが、その時私は何を言っていたかというと、ダンスが何かとか説明できないので、「とにかく一緒にやってください」と言って動き始めた。で、誰もついてこないんです、もちろん。そういう悲壮というか、とにかくもう一生懸命やるしかない、乗った船が動いてしまった、みたいな。きっかけといっても、最初はそういう状態でした。
ただ、なぜ引き受けられたかというと、「この人たちを舞台に上げたい!」っていう、主催者の方の強い思いがあって。ダンスをやることで何か効果が、とか、この人たちの可能性をもっと、というようなことを望まれたりするのかなと思いきや、この人たちを舞台に立たせて弾けさせてほしいっていうそれだけだったので、それなら自分自身もやってきてて、その楽しさを知っているし、難しい障がいのことはわからないけど、とにかくあのスポットライトの中へ行こうという感じで始めました。だから今も、関係としては私が彼らに何かを教えて取得してもらうというより、この日が発表だからそれに向かうぞ!って、全員で同じ方向を見て、とにかくワーっと走り続けている。そういう8年間かな。
長く続けていると、同じやるんだったらもっと楽しみたい、ええかっこしたいとか、あの人よりも長く舞台に残りたいとか、みんなそういう欲求が出てくるんですね。じゃあもっとやる?みたいな感じでやってて。最初のころは、自分の作品とWSをすごく切り離しているところがあったんですけど、続けていくうちに、全然境目がなくなってきました。今、自分自身が舞台に立つために必要だと思っていることは、全くそのまま彼らに対してもやっていますし、逆に彼らがやっていることから刺激を受けて、自分自身が舞台に立っているっていう。そういう関係にやっとなってきたのは、本当にここ2、3年かな。
-砂連尾さんのきっかけというのはどういうことでしたか?
砂連尾:地域との関わりということでは、1994年に中京青少年活動センター(旧中京青年の家)で、主に初心者を対象とした、30歳までの京都市・府の在住者のWSですね。ただ、コミュニティダンスという文脈で考えると、2003年に京都府宇治市の平盛小学校で、当時その学校の教員だった糸井登先生が、運動会の組み体操を創作ダンスでやりたいと、僕と寺田みさこさんに依頼がありました。そのWSは3週間ほぼ毎日、3時間~4時間の時間を何とかつくっていただいて行うという、結構本格的なWSでした。その平盛小学校との関わりが、僕にとっては地域やコミュニティダンスとの最初の出会いだったと思います。
-どうしてその依頼があったのでしょうか?
砂連尾:糸井先生が勤めてた時代は、多様な問題を抱えた地域で、かなり学校が荒れてたんですね。その状況で、学校の授業や学校の先生では救いきれない生徒に、グループでダンスの創作することを通して、なにか普段先生たちが出来ないことをアーティストにやってもらいたい、ということで私達に依頼がありました。恐らく、それは僕が主に関係性ということをテーマにしてダンスを創っていたことからの理由だったのだと思います。今振り返ってみても、その学校での体験は、僕はその後も、いくつかの地域の小学校に行きましたが、授業で本当に背後から蹴られるんじゃないか、殴られるんじゃないかっていう恐怖感を抱いたのはその学校だけでした。
-小学校なのにそんなに荒れているのですか?
砂連尾:体育の授業など、先生が騒いでいる生徒をガンと壁に生徒を押さえつけないと、収拾が付かないっていうことも時にはあるぐらい荒れている小学校でした。不登校だったり授業に来ても殆ど教室にいなかったりとか、また教室をずっとうろうろしてる子もいると聞いていました。
そんな状況の中、ある男の子が、僕らのWSを最初からずっと遠巻きで見ている子がいたのですが、その子に対して僕も距離をとりながら、「見ているだけでも良いよ」とか、たまに「やる?」と導きながらWSをしていたのですね。そうしたら、その彼がどんどん近づいてきてくれて、発表会前日には自分の動きを朝礼台でやってくれたんです。それを見て僕は、彼の動きを全校生徒が真似るシーンを急遽作りました。それがなされた瞬間に、糸井先生は、「あのシーンが見れた時にもうこれで充分、本当にこの企画をやって良かった。僕たちが彼らと対話しようと思っていた事が、やはりそれは言葉だけではなくて、体の動きを通してコミットすることなんじゃないか、そのきっかけを彼自身も作れたんじゃないかと思った。」ということを言ってくださいました。(3週間のWSでは、もちろんそんなに大きな問題がある学校ということまで分からないんですが、僕自身はこの体験が、コミュニティダンスというのかな、身体が持つある繋がりをつくっていくということや、言葉ではなく体の行為を通して、何か出来るんだということが、すごく大きな実感として沸いた最初の大きな仕事であり、その後この動きへと、参加させてる大きな出来事だったような気がしますね。)→僕自身はこの平盛小学校での体験がコミュニティーダンスの可能性を実感できた最初の大きな仕事であり、現在も継続しているこの取り組みへ関わる大きなきっかけだったような気がします。
-それは大きなことですね。その男の子がそういう風に変わってきたのは、何かきっかけがあったのですか?
砂連尾:とりあえず、無理やり参加はさせなかったんですね。彼が居やすい位置で、見ているも良し、加わるも良しという状況、環境を作りました。僕は、見ているってこと自体も充分な参加だと思っています。それと、そのWSには、寺田さん以外にその当時、非常勤で勤めていた京都造形芸術大学の学生が常時4~5人ボランティアで参加してくれました。学生は彼に限らず、他の生徒にとっても親しみやすい存在だったと思います。それからWSに参加しなくても、教室の中に彼が居やすい場所、居られる時間、誰かに寄り添えるような環境をつくっていたということも大きかったなと思います。まず自分の場所をそれぞれがつくれる環境にあって、それでWSには入りたいときに入り、抜けることも自由に設定をしておいた結果、彼自身が徐々に心を開いていき、一歩を踏み込めるような雰囲気が作れたのかなと思います。
-先生方の反応はどうでしたか?
砂連尾:糸井先生以外では一人協力的な方がいらっしゃったんですけども、その先生以外は殆ど、まずコンテンポラリーダンスのアーティストって何者?っていう猜疑心の目を持っていたのではないでしょうか。ただそんな状況の中、糸井先生は僕たちが気持ちよく仕事し、きちんと力が発揮できる環境をつくってくれました。それは例えば、そのWSが始まる以前から、両親への配付物に「授業でこんな事がおこります。こんな人が来ます」というのを配ってくれていましたし、また毎日帰る時間にはその日に実施したWSを写真入りで「こんなWSをしました」という稽古日誌みたいなもの結構きちんと書いて、生徒に渡してくれていました。そのことで、今いったい何が起こっているのか?ということを生徒の親が分かるような状況をつくっていました。その説明がまず親の不安を取り除きましたし、そのことで周りの先生も一応OKみたいな雰囲気作りを、糸井先生はかなりきちんと丁寧につくっていたのではないかと思いますね。
-先生方の反応が、終わってから少しは変わったということはありますか?
砂連尾:そうですね、やはり「やってよかった」「この子達があんなふうになるとは思わなかった」と言って下さいましたね。親御さんも、「組体操とは全然違うし、みんなバラバラな動きをしているけど、みんな楽しそうで良かった」など、肯定的な意見がすごく多かったですね。自分の子が生き生きしてるっていうことで、それまで見せた表情とは全然違うっていう意見もありました。
+++
-続いて北村さんに、先ほどの続きをお聞きします。今日、実際にWSを見させていただいて、よく言われることですが、障がいを持っている人たちでも一人づつの障がいは全然違うし、一人一人の反応も違うし、ただ一時間半の中で、とにかく一人一人が反応して、元気で、混沌としている中にも何かに向かっていく力みたいなものを、すごく感じました。北村さんの心持ちも含めて、8年間続けてきたことで、何か変わってきたことというのはありますか?
 北村:私自身のWS経歴と、彼らと関わっている経歴というのが、ほぼ同じぐらいの長さになります。彼らとの関わりの中で、私自身のWSが開発されてきたし、考え方もすごく変わってきたところがあると思います。まず言葉を使わずに誘導していくというスタイルは彼らとの関わりの中でできました。今日の参加者の中には、聴力のない方がいます。おそらく、殆どの人が言葉の意味を理解できないと思います。
北村:私自身のWS経歴と、彼らと関わっている経歴というのが、ほぼ同じぐらいの長さになります。彼らとの関わりの中で、私自身のWSが開発されてきたし、考え方もすごく変わってきたところがあると思います。まず言葉を使わずに誘導していくというスタイルは彼らとの関わりの中でできました。今日の参加者の中には、聴力のない方がいます。おそらく、殆どの人が言葉の意味を理解できないと思います。
私、一人一人の詳しい障がいについてはほとんど知らなくて、今だにそれは知ろうとは思ってないんです。医者でも専門家でもなく、私は振付家です。さっきも言ったように、目的は彼らの障がいをなんとかしようとすることではなくて、一緒に舞台に立つことなので、人間同士の一対一の関係が作れれば、それで充分なんです。関わりの中で相手のことを知っていくということは、それは障がいのある無しに関係なく、一緒に作品を創るなら普通にすることで、必須でしょう。そういうふうになってきたときに、彼らの欲求と私の欲求が、どんどん高まっていく中で、彼ら自身に、舞台に立つんやったらこれぐらいはやりたいとか、何かこれじゃだめだみたいな、美意識みたいなのが生まれてきたんです。
毎年音楽祭をやっているのですが、3回目が終わったころに一回、私が振付のみで関わる回があったんです。全体を演出する人がいて振付だけ任されたときに、私も言われたことを彼らに伝えなくてはいけなくなって、言葉の指示がすごく増えてしまったんです。明らかに普段と違うというのを彼らはすごく感じて、パフォーマンスのクオリティとか、モチベーションがダーンと落ちたんですよ。今までしゃべらなかった人が、急に嫌な顔をするとか、あからさまにその態度や身体に、変化が見え始めた。いい時ばっかりではなく、やりにくいとか窮屈だとか、これはしんどい、というのを通過した先に、なんかあるのかな?と。それがあって、本当の意味での関係作りが始まったと思います。
彼らは特にそれについて感想を言ったり語ったりはしないんですけど、ただ欲求として「これしたい!」とか、普段のWSの中でも言うようになってきた。そうなってきたときに、それまで「これ以上は無理かな」とか、彼らのためにわかりやすくとか、しんどくないように、と思ってやっていたことを止めたんですよ。そこから彼らの変化が大きくて。 例えば、最初に始めたころって、ほとんど全員が動かなかったんです。90分棒立ち。私一人がグワーって動いていて、当時は私もアシスタントがいなかったんで、主催者の事業団の担当の方がアシスタント代わりに、「とにかく一緒に動きましょう」とやってくれて。一番大変だったのが、職員さん。送迎とか介助を理由に「何で私たちが踊らないといけないのか」と言われて、とにかくごり押しで「この部屋にいる人たちは全員踊らないとダメなんです!」って一生懸命言うんですけど、ちっともやってくれない。その職員さんたちが、自分の意思でこの人達と一緒に踊るようになっていただくのに何年かかかりました。
今日のWSではたぶん、誰が職員で誰が障がいのある人たちで、だれがこっちから連れてきたアシスタントで、という境目があまりなかったと思いますが、最初はもう、バシーって壁があったんですよ。で、例えば私が立ったり座ったりして、自分の意思でそうやらない人の手を無理やり引っ張ってさせる。職員さんにとっては、そらそうですよ、それがお仕事ですし。それで参加者が余計に嫌がるとか、とにかくぶつかりまくってたんですね、最初は。でも障がいがある人達のワークだけじゃなく、最近つくづく思うのは、難しいと言われる事は実は一つもなくて、根気がいるんだと思うんです。成立するまでやり続ける、っていう。そこで、まずしんどい思いをしなあかんというだけで、難しいと思っていることが、実は一番の障がいであり障壁なんだと思います。
小学校に行かせていただく機会も多いのでよく耳にするのですが、例えば先生が「これは難しいですね」て言ってしまったら、難しいことになってしまうんです。言葉は良くも悪くもすごく力があって、どういう関係の誰が言っているかということは、すごく大きい。そういう意味で、言葉を使う、使わないという選択も含めて、すごくデリケートな問題。その言葉の使い方を、今関わってる知的障がいの彼らからすごく教えてもらったんです。言葉は通用しないとか、言葉がここでは要るとか。

-なるほど。今は、北村さんの普通のWSでも、始める時に何も言わないですよね。今日の障がい者とのWSも同じで、北村さんが座ると、何人かが座り始めて、いつの間にか全員が輪になって座っている。これは何年目ぐらいから?
北村:ここ2~3年かなあ。最初は私もわからなかったので、集まってください、真似してくださいって言ってたんですよ。でも3~4年やっても何も変わらないし、棒立ちの人はずっと棒立ちだったし。でも最初は、棒立ちでもこれは何か意味があるとか、この人はこうやんね、ということを何とか見つけ出して言ってあげたりしていたんですが、本人がそれを感じてないから全く意味が無いんですよね。相変わらず変わらないな、じゃあ何が足りんのかな、何がいらんのかなということを、1人ずつ見ていて、「理由が無いんやな」ってわかったんです。必然を作らんとだめなんやと。彼らが欲しているのは、踊り方とか、こうしたらこうなる、ということではなくて、仕方なくそこに向かわないといけない理由というか、仕掛けを設定してあげることかな、と思って。それで全くしゃべらなくなったんです。そうすると、さすがにみんなも意味がわからないので、いろんな反応があって、私がしゃべれなくなったのかと、ずっと不安そうにくっついている人もいたり。職員の皆さんもよく付き合ってくれたと思うんですが、最初に座って集まるのに、1時間ぐらいかけてやったこともあるんです。とてもダンスのWSとは言えないような状況があった。それもすごく根気のいることで、「これじゃダンスの仕事を何にもしてない」ってクビになるかも知れんけど、それでもええわって覚悟を決めて、とにかくガンと座るみたいな。でも何回かやっていくうちに、なんとなく気が付いた人がやり始めて。職員さんとの関係もそこで築けたんです。職員さんには最初から、なぜこんなことをやっているのか、何をさせようとしているのかということを、言わなかったんですよ。というのは、言ってしまったら、職員さんが「こっちやで」ってサポートしちゃうでしょ。それは職員さんの役割として日常的にやってることだから。でも職員さんにもそれをさせてはいけない。そんなことに労力を費やさなくていいような状況をつくってあげたらいいんだなって。そんなこんなでつくられてきたことですね。
-なるほど。北村さんなりに自分のダンスWSのスタイルをつくる上で、この8年間の彼らとの作業は大きいですね。
北村:すごく大きいですね。やはり最初は教えていましたし。「こうやるんですよ」みたいなことをやっていた。
-先生だったわけですね。
北村:そうです。今のスタイルになる過渡期のときのことですけど、癲癇を持っていて毎年のように本番直前になったら楽屋の廊下で発作を起こす方がいて。初めての本番の時とは舞台上で発作が起きたりもして、自分でもそうなったら皆に迷惑がかかるし、発作はしんどいから、やめる、やめると言いながらも、3年ぐらい参加して下さって。最後に、稽古期間中もリハも本番も、一回も発作が起きずに本番をやり遂げて、それで満足して今はやめられたんですけど。なんとなく関係で分かるのですが、最初はたぶん、やりにくさを感じてはったんですよ。でも最後、本当にのびのび自分がやりたいことをやりつくして、しかも発作もでない。そうなったときに、その人はもっとやるという発想ではなくて、もうこれで卒業、もうケリがついたと。で、本当にありがとうございました、とその方の言葉で言いに来てくれて。そのことが私にとってすごく大きなことでした。
お歳で体も大きくて、発作も持っているし、できないことがたくさんあって、でも、私よりもずっと大人だったんですよ、その方のほうが。場がそうなっていく事を、その方は見届けてくれたのかなと。で、その年の振付や課題も、私はこれ以上はできないけど、絶対これ以下にはしません、と毎回きっちりやり遂げて帰る人で。本当に最後のパフォーマンスは感動的で、一方的に何かをするっていうことでは足りないんだな、ということを、その方との3年間で教えてもらったと思います。
To be continue……
JCDN
最新の記事 JCDN (全て見る)
2014年5月15日