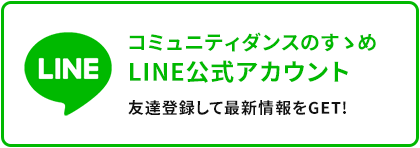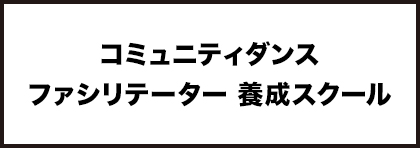マニシア インタビュー第1部
2007年1月、福岡を拠点に全国で活躍中のマニシアさんに
JCDN佐東がインタビューをおこないました。
『マニシアさんのすべてがわかる』4部構成!!
+ + + + + + + + + +
第1部
―マニシアさんの活動について教えてください。活動というか略歴的なところから。
マニシアさんがダンスを始めたのはいつからですか?
5歳です。
―それは親に連れられて?
親が日本舞踊をしていたんです。
―それは福岡で?
いえ、大分県の日田市です。すごく田舎です。
おばあちゃんも日本舞踊をしていて、日本舞踊をするようになっていたんですけど、ある時どういうわけか招待券がふっと来たんです。見に行ったら、映画の「ジャングル探偵レオ」をやってたんですよ。それで「あー映画いいなー!」と思った後にバレエがバーッと出てきて、うちの母親がその数日後、「着物を着て踊るのと、ドレスを着て踊るのとどっちがいい?」って聞いたから、「ドレスー!」って5才の私が言ったんです。それで母が「ドレスね」ということでバレエをはじめました。でもそのバレエの先生は小学校の校長先生で、バレエっていうか創作ダンスのようなものでした。
―バレエといっても創作ダンス?
校長先生で戦後子どもたちが赤線とかいう所に行かないようにって、教室を借りて“人間教育が入ったバレエ”みたいな感じでやってたんですよね。
―なんでまた赤線と子どもたちのバレエが?
なんかモダンダンスをつくった方が日田に来たらしいんですよ、名前は知らないですけど、聞いたらわかりますけど有名な方が。それで「うわーすごいなー!」と思って自分もやりたいなと東京に行って、なんとなく覚えて帰ってきて、それでなんかバレエっぽくなってきて。
―じゃあその時代だったらマーサ・グラハムか誰かかな。
いやいや違いますよ。もうなんか、舞踏みたいな人ですよ。土方巽?
―土方さんではないでしょう。
ですかね。今私の先生は83歳ですよ。なんか日本人の男性でした。
―そうか、アメリカに行って帰ってきたモダンダンスのはじめの頃の人だね。
そうですね、多分ね。それで先生もやっているうちに「これは」っていう感じで、多分やっているうちに響いたと思うんですね、そのやって何かに集中すれば、子どもたちが不良をしない、みたいな。神社の講堂だったし、その波動的にもすごく良いんですよね。古-いし。でもバレエとか言いながら裸足であったり。それでなんかこうタンバリンを使って、ポーズづくりみたいな。だから基礎とかあまりないんです“バレエ研究所”なのに。でも、そこが心地良かったんですよね。弟子たちが、もっともっと学びたいからって東京に行き、それでクラシックバレエとかを学んで帰ってくるわけですよ。私の先生は年を感じていたのか弟子たちが教え初め、そして研究所が「かたち」を学ぶ場所になってくるんですよね。でも私は他のどこにも行けないから田舎だからそこしかないから続けていましたが、足のポジション1番とか2番とかいうのも学びながら、トウシューズとかもはきました。しかし、負けたくないから一生懸命やっていくんだけど、でもやっぱり『裸足でタンバリン』っていうのがずーっと好きなんですね、やっぱり。
―でも変わってるね。変わったスタジオがはじまりだったんだね。
でもその年代ってそうですよ。
―だから今みたいなバレエ教室がカクッとしてない時だね。時代としては。
そうですよね、だから私の場合はそこで種を植えられたみたいな。
今思えば、その種があるから色んなことをやってきて、バラバラみたいだったけど、何となくまとまり今の自分があるんだなーって先生に感謝していますね。多分そこでクラシックバレエから入っていたら、私の気質からいくと人生そのものに混乱してたかもしれません。
―そうだね、抜けられなくなったかもね。
まあほら、ジャズダンスとかいうのもあったじゃないですか、流行りの中で。やっぱり自分も若い時ってそういうのに憧れるじゃないですか。それで本物を習うために東京に行ったりとか、本当に学ぶならやっぱり西洋人だなーっていうのがあって、「どうせだったらニューヨークだ」ってニューヨークに行って。
―それは高校卒業したあとに?
えーといや、短大卒業後ですね。短大に入る前は“ダンス”とか“人生”とか色々考えてはいましたが、たくさんの可能性の中からひとつ心に響いたのが「子どもが好きだなー」という気持ちがあり保育科を選択しました。
―ちなみにそれは何歳?20代半ばで?
短大在籍中、東京へ行き来があり、20歳で卒業してからですね。夏休みにアルバイトとしてその研究所で、先生たちが結婚などでいなくなったから、私がダンスを教えていたのです。でもちょっとジャズダンス的なのもありながら、みたいな。やっぱり私の先生がもう年老いてきたので、お母さんたちが若い先生を欲しいわけですよね。それで卒業とともに私が帰ってこないと子どもたちを辞めさせる、と言い出して。「まあ子ども相手だから保育士でも、ダンスの先生でも一緒かな」ということで実家に戻ってダンスを教えることを決めました。途端にうちの母が「あなた箔を付けるためにニューヨークへいってらっしゃい!」とか言い出し私は「は?ニューヨーク!?」みたいな。
―そうか、じゃあお母さんに言われて行ったんだ。きっかけ的には。
そうですね。
―日本舞踊で、やっぱり何が必要かって事をわかっていたからだろうね。もうちょっと外の血が必要だ、みたいな。
そうですよね。それで、行ってまあ本場のジャズダンスを学びたいという目標もあったし、行ってみようかという気になり、アルビン・エイリーに入りました。そしたらもう、刺激いっぱいですよね。教えることに興味はあるけれど、私はダンサーでいたいって、まだ若いから思うわけですよ。
―アルビンエイリーにしても、本当に初期の頃ですよね。
そうですよ。そうですそうです。
―ニューヨークって行っても今のニューヨークじゃなくて、もっと荒々しいニューヨークですもんね。
はい、もう大変な。映画の中の混乱したニューヨークに自分がいるみたいな。
それから戻ってきて、子どもたちにモダンバレエ、大人にジャズダンスの指導を始めました。本格的に身体でしっくりいき始めたのは、戻ってきてからでしたね。やっぱりその指導っていう中で学んでいくわけですよ。毎週だれかに見られるという緊張感もできてくるし、そこから自分自身の身体と向き合い伸びてきたかなーと思いますね。
―何年くらいニューヨークにいたんですか?
1回目から戻ってきてすぐ、やっぱり自分はもう一度行きたいと思い、1年後に行ったのかな。もう行き来が継続しあっという間に10年近くって感じでした。その間に長期留学も2回くらいありましたね。そのうちに振付家のルビー・シャングに出会ったんですけどね。
日本に帰ってきている間に、アメリカンダンスフェスティバルが東京でまだやっていて、日本にいる間も、レッスンしたいからという思いで東京のアメリカンダンスフェスティバルに行って、その時にルビーに初めて会ったんです。それで私がちょうどニューヨークで留学している時に「私がニューヨークにいるよ」ということをルビーがだれかから聞いたらしく、彼女もちょうど作品に東洋人が欲しいと思っていて「是非いらっしゃい!」みたいな感じでルビーとの活動が始まったんです。
―ルビーとの活動はどのくらい続いたんですか?
5年ぐらいかもやったかも、5年ぐらいはありましたね。
―結構、密に?
はい。初めというのが、4回ぐらいのリハーサルでもう本番だったんですけど、そういうのって自分としては初めてだったんですよね。即興とかいうのもやり始めたばかりの時期で、これでいいのかなーという感じで作品に入れてもらったのですが、本番にパーン!って忘れてしまって、もういいやっていう自分がそこで初めて出来上がって、即興をワーッとやってしまいました。終わって多くの人からたくさん褒められて「あ、これでいいんだ」って何かが開きましたね。それまでは日本的に「これはこうじゃないといけない」という形づくられた作品っていうのが、いつしか自分の中にあり、それしか知らなかったんですね。そこの経験が、なんかこう大きなふたを開いてくれたというか。
―80年代がずっとニューヨークと日本の往復ですか?その頃はまだ日田にいたんですか?
そうですね。そうです。
―日田からニューヨークへ行ったんだ。
アハハ、すごいですよね。でも日田の人って結構すごいんですよ。私が小学校の頃のバレエの先生、もともとの先生の弟子なども現代舞踊で文部大臣賞を受賞したり、違う弟子は東京でモダンバレエ研究所を開いたり、だからもともとの先生が教えた弟子たちって、結構やってるんですよ。
―そして90年くらいに?
えーと89年に子どもを産んで、もうやっぱり子育てができないっていうので90年に帰国しました。
―戻ってきたっていうのはアメリカから日本に?
日本に。それで日田に戻ったんです。
―89年に子どもが出来て、もう日本に帰ろうと?
そうですね。6ヶ月いたんですけど、ちょっと何かあった時のためとはいえ目つぶしスプレーをもっている生活は続けられないなーと思ったんです。抱っこしていては、逃げられないなと思ったんですよ、本当に怖い時代でしたから。そのまま抱えて踊れないし、クラスに連れて行くにも、片隅においておくだけでも危ない時代だったので。
ニューヨークでバンバンやってるダンサーのひとりになりたいと踊っていたのに、妊娠とともに自分自身すごく変わりました。でもやっぱり臨月ででもバンバン踊りたいという気持ちはあったんですね。そしたら同時期にルビーが妊娠していて、ルビーに公演の話があったんです。15人の妊婦ダンサーと一緒に踊るっていうのが。でもルビーはお腹の赤ちゃんを失いたくないから、代わりに私に出演したらって言ってきて「是非やらせてもらいます!」みたいな感じで即答しました。そしてリハーサルが始まり出し、人や空間の波動が全然違うことに気づいたんです。リハーサルが進んでいくうちに、ニューヨークのダンサーたちって自分が1番みたいなセンター争いがあり、気がついたら私もそうなっていとのでしょう「即興やるといつもぶつかるのは何でだろう?」と長い間感じていたんだけど、「センター争いだったか」って気づいたのはこのリハーサルに参加し始めてだったような気がしますね。自分の身体はもちろん、相手の身体を守る空気を感じたんです。

『生命』というものを考える表現者たちが15人集まったわけですよね。その中でアーティストとか、ほとんどがダンサーだったんですけど、偶然にもですね。「どう?」見たいな感じで5分毎に皆休みたいとか、5分毎に何か食べたいって言う人が出てくるんです。「じゃあそろそろダンスやろうかなー」という生活の中にダンスが入っているっていうリハーサルだったんです。場所が教会ということもあってなんかすごく「ダンスって神秘だなー」みたいな感覚も公演の際には味わいました。
その中に昔私がジャズダンスのクラスで会ったバリバリのジャズダンサーがいたんですよ。彼女は母親になる準備ができていたように感じだったし、その人の変化を見ると自分も変化したんだなーって、なんだかすごく自信をもらいました。後になって思えば、そこで自分が生きていく道を見つけたというか、ダンスを含めた人生で大きく変わった時期ですね。
その4日間本番をやっているうちに、5日目に出産予定日を抱えた人も出ているんですよ。私はちょうど臨月に入った時期だったのですが、公演が終わったその後に「バスタブで産んだよ」なんていう情報を聞くと、なんかもうずーっと続いている、作品が終わってそのままじゃなくて、なんか生きていくことの中にダンスが入っていて。もう「準備段階からが踊りで、終わってからも踊りだよ」という、なんかすごく違う感じでありながら実は、とても自然でうれしくなる感じがしましたね。枠があるのがダンスじゃなくて、流れがダンスという風に、その頃から変わってきましたね。
―その経験は大きいね。
大きいです、かなり。それでやっぱり自分の中で踊り続けたいっていうのがあって、福岡に帰ってきて「抱えて踊る」みたいなのが始まったんですよね。
―なぜその時、日田じゃなくて福岡に来たの?
日田に一度帰ったんですけど、国際結婚なので、主人が追いかけられるんです、子どもたちから。まだ外国人がいなくて「ガイジン、ガイジン!」って追いかけられるんですよね。だから自分たちの子どもにそういう思いをさせられたくない気持ちがあって福岡を考えました。ちょうど“ヨカトピア”っていうお祭りが福岡でやっていて、そのお祭りに行ったんです。そしたら外国人がいっぱいで、その流れでいっぱい外国人が福岡に住むようになっていて、じゃあ福岡かなーというので福岡に引っ越してきたんです。流れ、流れで。
―旦那さんはダンサー?
はい、ダンサーでした。マーサ・グラハムの初めての相手、エリック・ホーキンズのカンパニーでした。そこで踊っていましたね。生活の為にもう英会話の先生になってしまいましたけど。でも初期は一緒に舞台で踊っていました。本番に来てくれる、彼は即興する、みたいな。でもやっぱり夫婦はケンカします。だからそれはもう徐々に一緒に踊る事がなくなってきましたね。
To be continue……
JCDN
最新の記事 JCDN (全て見る)
2013年9月2日