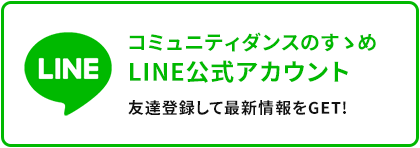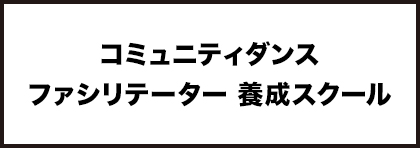マニシア インタビュー4部
2007年1月、福岡を拠点に全国で活躍中のマニシアさんに
JCDN佐東がインタビューをおこないました。
『マニシアさんのすべてがわかる』4部構成!!
+ + + + + + + + + +
第4部
―今回のセシリアとの出会いはどうでしたか?
セシリアとの出会いは、彼女がアートセラ ピストで、ダンスの舞台をつくり上げていって、セラピーと芸術というのを一緒にしていいんだという自信をかなり得ました。「これでいいのよ、マニシア」み たいな。リズの時にはまだまだ分けていた自分があって「ダンスってすごい、でもセラピーもある、勉強したい」というのがあったんですけど、もうセシリアは 全部一緒にしてますし、彼女のみんなを導くツールというのがセラピー的であるので「そうでいいんだ」みたいな。「もう素直な自分でいいんだな」「自分は自 分のありのままでいいんだな」みたいな。だからこれからスタートしていくのは、自分のやり方というのがそのままでいいんだし、というギフトをもらった感と いうか。
―そしたら良い出会いだったんだね。
良い出会いでした。かなり母親としてもお互い似てますし、人間的にも目指 すものが似てるような。交流を続けていきたいので今回オックスフォードに行きたいなと思います。彼女のやり方を彼女の土地でやっているというのをすごく見 たくて、彼女のカンパニーでやっているものも見たくて。そして私が福岡でやっているっことを彼女は一部見ているので彼女のあり方を彼女の国で見て『交流』 していきたいですね。私自信は西洋の社会にすごーくこの日本的な考えをハーッと変えられたので、子どもを連れていきたいなという思いがあって、交流はリズ の時とかから始まっているんですけど。子どもがアメリカに着いた途端に「においが違う」って言ったときに「これこれ!」って思ったんですよね。やっぱりそ のにおいが違うっていう感覚からダンスを始めすべてが変わってくると思いました。
―子どもをもっていきたい、というのは自分の子ども?それとも今一緒にやってる生徒?
生徒です。「この指とまれ」で誰かがツアーに参加すると思うので、向こう に行って「こんなんでいいんだ踊りって」という、今モダンバレエなので結構カタチカタチ、テクニック、みたいなのがあるんだけれども、即興ってあまりやれ ないんですよ子どもたちって。日本の社会の中で「恥ずかしい!」っていうのがいっぱいあって、やったらどう見られるかなという自分があるらしく。そういう 子どもたちがいっぱいいるので、そうじゃないっていう社会もつくれたらと思いますね。
―さっき言っていたダンサーたちが、たとえば障がいをもった人たちとワークをすると、そのダンサーたちが変わっていくんだっていうことを実感したというのは、どういうことですか?
感性です。感性との出会いですね。「こんな感覚」っていうのを、プロのバレリーナがほとんどなんだけれども、古い作品の 中でずっと学んでいるんですよね。感性というの学ぶんです。でもやっぱり舞台をやりながら、舞台のちからで、自分自身との出会いっていうのを体験してきて 素晴らしいと思うんだけれども、もっと奥深いそれぞれの感性との出会いっていうのが、障がいをもった人たちからちょっとした身体的表現で「あ、こうでるん だ」みたいな驚きがいっぱいでてくることを感じ、その驚きの中で彼女たちが私も得た「これでいいんだよ、ありのままでいいんだよ」という、OKを出せる自 分との出会い。「こうじゃないといけない」っていうのが少しでも柔らかくなるといいんですよね。感性の中に自分をどっしりプロダンサーとして入れてると思 うんですね、プロ意識というか。でも結構人間的な「それでいいんだよ」って言えなく自分にOKだせない自分を作り上げているんですよ。そこですかね、そこ の改革。あー人間だったて心から思い出すみたいな。だからもともとの感覚が開くと「こうじゃないといけない」の中に真の自分を入れ、この四角が楕円形にな る、感覚が。そうすると楕円形の感覚をもつシャープな動きとか楕円形の感覚をもつ四角い動きが何か細胞的に変わってくるんですよね。光をもつような。

―たとえば一般の人もそういう感覚を持ってるはずだし誰もが持っているはずと思うんだけれども、なぜそこで障がいをもっている人たちからその感性というものを得られるんだと思いますか?
健常者だと何かと表現のテクニックをもっているんです。偏った方法と言うか。ほとんど表現が十字にしか感じられないです よね。お決まりの縦と横。でも多くの場合、障がい者だと生活が違うのもあるんだろうけど、ここはまだ分からないんですけど多分人間的に愛をもって育てられ ているんです。まず母親がショックを受けて、自分の子どもが障がいをもっている、というところから母親が乗り越えるんですね。そして乗り越えると、父親か もしれないけど、乗り越えると“大きな愛”というものが芽生えて「生きるとはシンプルだ」という感覚を得て、子どもを育てる。もともとの人間のちからとい うのがよりついてくるんですよね。子どももその過程を肌で感じてるし。現代人には感覚というのが、言葉にはできない感覚といいながらお決まりの種を植えら れているんですよね。十字の表現に慣れている私たちには障がいのある人のスパイラル的で、空間とか時間とか計算とかなくって「こうじゃないといけない」っ ていうのを省いたものが目新しく感じるんですかね。本当は大人になっても子どものように自由でいいのに。
ある意味ダンスWSの中で、演劇の人たちが入るのもすごく面白い んですよ。何か超えている部分がありますね。驚きがいっぱいいっぱいあって原点に戻されるっていう驚きみたいね「たしかにそうだよね!」っていう感覚はい いですね。人間を演じてるからこそ、人間のそうあるべきを知っているというか。繰り返しですね、ワレワレワークスも。だからなんか舞台裏がすっごく面白い ですよ。その舞台というのを実験的に、セラピー的な効果があるんじゃないかっていうので福祉とつながって、大きなグループとコラボレーションして、もうす ごく大変だったんですけど、セラピーセッションをやってきたグループを舞台にのせたんですね。そうするとやっぱり彼らが楽しむというのは、本当にメイクで あったり、ちょっと髪を動かしてもらうことで、本当にその1日が彼らにとっては一生の宝物なんですね。そして楽しみがシンプルにずーっと続いているという のを知ると「舞台って面白いなー」と思います。それに関わるスタッフの人たちが「自分たちも踊りたいよね」「待つんだったら踊ればよかった」みたいなこと も言ってましたし、楽しむことを彼らから学ぶんですね。
―そういう意味では、福岡に工房マルがあったというのも大きいね。
彼らの仕上げというのも、すごい目標でもありますね。ただ単に落書きをしたものも、すごーく上手にひろって、それをなん かお洒落な枠をつくっているとか、お洒落なグッズの中にチョンと入れている感覚っていうのは、これはもう舞台でやりたいよねー、ていうか隠せない部分だ なーていうか。
だから「踊る工房まる」みたいな目標があったから、よかったんですよね。先にやられていたら多分挑戦したくなかったと思うんですよね。絵画でありダンスじゃなかった、というのはすごくよかったです。
―セシリアとの出会いで1番感じたことは?
障がい者との出会いですごくハイになっていた、その感性の部分を探る自分が、こだわりすぎていて健常者ということを忘れ ていたんですよね。そしてその中でも同じぐらい素敵なものがあるということを彼女は教えてくれて「あ、そこに視点を忘れていたな」もっと総合的なものをセ シリアは知っている、と思いましたね。だから今後の自分の楽しみがもっと広がって、そこが贈り物だったんでしょうね。
―ひとつ剥くと次の皮が見えるという感じで、そこが面白いね。
だからコミュニティダンスって「何のために」って、コミュニティの活性化とかダンスを広げるためにとかじゃなくって、結 局「この指とまれ」って言った人がワクワクする、そして知らないうちに活性化されて知らないうちに人が楽しくて幸せになっている、それを見て「この指とま れ」って言った人が「やってよかったな」みたいな。だからただスタートするだけで、ずっと続いているわけですよね。
―それはなんか不思議だよね。
不思議ですよね。だからどこからどう起きてきたか分からないんですけど、でも社会が生んだことですよね。社会が生んだこ とだから、だから面白いんでしょうね。「これをやりたい!」って言った人が始めたことじゃなくて、やっぱりクラシックバレエとかモダンダンスとかコンテン ポラリーダンスもそうですけど「こういう形でありたい」といって始まったから。でもコミュニティダンスって社会が生んだことだから。コミュニティダンス じゃなくてもアートであってもビジネスであってもいいんですけど、なんか社会がつくり上げたもので、後で人間が入ってくるので、初めが個々じゃなくて終わ りも個々じゃないので面白いですよね。
それを言葉に分解していったり、それをカタチにしていくというのは、結構気をつけないといけないことですよね。また枠になってくるので。たしかにこれくら いの枠を作らないと危ない部分でもありますよね。「右向いて右がコミュニティダンスです」という人も今からきっと現れてくると思うんです。

―そこでマニシアさんのいう、コミュニティダンスが枠として捉えられる危険性というのは、どういう部分ですか?
枠が核であるといいんですけど、枠がそのまま継続するという方向性があると危ないですね。というのは、社会というのは ずっと変わっているじゃないですか。そして社会の中に生まれたコミュニティダンスの中に色んな人間が入りこんでやっているわけで、社会と共に変化するとい う可能性があるコミュニティダンスだとOKなんですけど、変化しない枠を作ってしまうと危ないっていうことですよね。だから枠というよりも核だといいんで すけど。
―その「枠」というのはどういうことなんだろうね?
グループとか組織とかがあるじゃないですか。そこを柔軟にすることかな。今から先の課題として。「私たちはこのコミュニ ティダンスというものを形成しています。だからあなたたちは入れませんよ」みたいな雰囲気を持つこと。本当に空気の通る透明的な枠ならいいんですけど、 やっぱり「コミュニティダンスとはこうです。こういうやり方があります」っていう方法論を中に入れていくのは必要性があると思うんですけど「あなたは入れ ませんよ」みたいなのだと、コミュニティダンスじゃなくなる。それはやっぱり社会が生んだものだから。社会は変化し続けるものだから。
―そういう意味で『47memories』は本当に広い枠でできましたね。
最高ですよね。すごく良くできたと思う。やっぱりカタチのあるものからスタートして、経験があって、カタチのないものに向かいながら枠が核になったところですよね。
―あとその時に思いついたことをやったというよりは、それぞれの人たちが やってきた事がそこに集まったような感じがしました。やはりマニシアさんのママダンスやパパダンスというものがすごく枠を広げたし、そしてそこにシニアの 人たちも入ってくる、若者もいる、という部分の広がりというのが、やはりそれまでの蓄積が幅広いというのはすごい事だなと思いました。
多分文化のレベルを見るとまだ知っている人が見に来る、というのが文化レ ベルなんですよね。だから課題であった集客というのはノルマを作るべきだと思います。たしかにそれはセシリアもやっているし、私もやってきた事だし。そし てノルマを作るには、という方法や人集めの方法「じゃあ、これがやりたいんだけれども、この部分を作ると人は来るよね」みたいなやり方っていうのは確か に、財団の方でももうやっていいんじゃないかなと思いますね。これだけカタチになったので。
―ありがとうございました。
END
(2012年3月 聞き手:JCDN佐東)

■プロフィール
マニシア/Manizia 振付家・ダンサー。
アメリカNYでのダンス活動後、90年に福岡に移り住み、「ダンスで国際交流」を目的にインターナショナルダンスネットワークを結成。子どもたちや親子の グループ、福岡住在外国人たちとダンス作品を創り上げ、13回に渡りストリートチルドレン救済チャリティー公演を開催する。現在は06年に結成した障がい 者とプロのコラボダンスグループWaLEwalewOrks(ワレワレワークス)と共に作品発表を継続している。05年ギリシャ、09年イギリス、11年 イタリアで開催されたヨーロッパアートセラピー会議でダンスの方法論の発表を兼ねたワークショップを行う。他、アメリカNY,コスタリカ、ギリシャ、イギ リス、イタリアで作品発表。http://dance-samadhi.petit.cc/grape5/
JCDN
最新の記事 JCDN (全て見る)
2014年5月15日